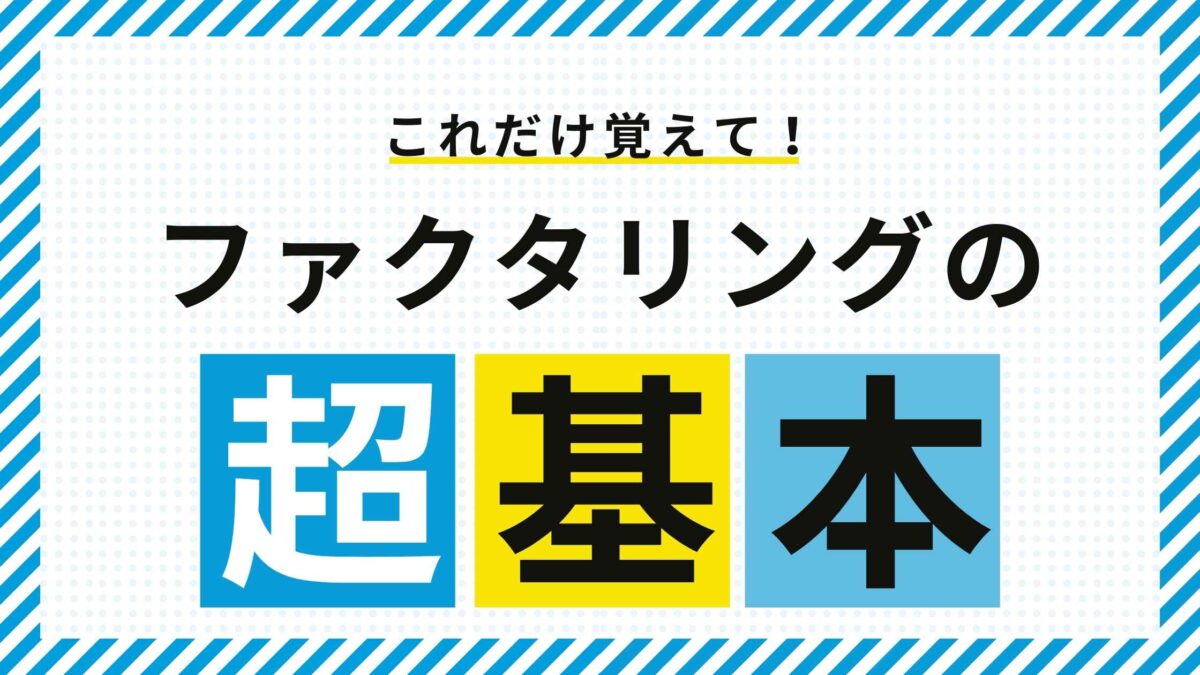ファクタリングの合法性の根拠:なぜ「借金」ではないのか
ファクタリングは「怪しい」「違法かもしれない」という印象を持たれがちです。これは、その法的な仕組みが正しく理解されていないことが原因です。実際には、ファクタリングは日本の法律に明確な根拠がある、確立された金融取引です。
民法第466条「債権の譲渡性」が示す法的根拠
ファクタリングを支える基本法は民法第466条「債権の譲渡性」です。この条文では「債権は譲り渡すことができる」と明記されています。
企業が取引先に対して将来お金を受け取る権利である「売掛債権」も、譲渡可能な債権に含まれます。
つまり、ファクタリング会社に売掛債権を売却する行為は、民法で認められた正当な権利の行使です。この取引は法的に「債権譲渡契約」と呼ばれます。
不動産売買や商品の販売と同じく「売買契約」の一種であり、借入金契約である「金銭消費貸借契約」とはまったく異なります。
この「資産の売却」という点が、融資(借金)との決定的な違いです。融資を受けると貸借対照表(バランスシート)の負債の部が増えますが、ファクタリングでは資産の部内で「売掛債権」が減少し、その分「現金」が増えるだけです。
そのため、負債比率が悪化せず、銀行からの信用格付けにも悪影響を与えにくいという大きなメリットがあります。
経済産業省が推進する国策としてのファクタリング
ファクタリングは単に法律で認められているだけでなく、日本政府が中小企業の資金調達を円滑にするための手段として積極的に推進しています。特に、経済産業省や中小企業庁はファクタリングを重要な政策ツールとして位置づけています。
多くの中小企業は資金調達を銀行融資に頼っています。しかし、不動産担保が不足していたり、赤字決算を理由に融資を受けられなかったりするケースが多く見られます。
この結果、帳簿上は黒字であっても売掛金の入金が遅れ、現金不足に陥り倒産する「黒字倒産」が後を絶ちません。
この問題を解消するため、政府は不動産担保に依存しない資金調達手段を広げようとしています。その中心的な手法が、中小企業が保有する最大の資産ともいえる売掛債権を現金化するファクタリングなのです。
2020年民法改正が後押し
2020年4月1日に施行された改正民法により、ファクタリングはさらに利用しやすくなりました。
改正前は、取引先との契約書に「譲渡禁止特約」があると、債権を他社へ譲渡できませんでした。
しかし改正後は、原則として譲渡禁止特約があっても債権譲渡が有効とされ、中小企業がファクタリングを活用しやすい環境が整いました。
この改正は、中小企業が売掛債権をより簡単に資金化できるようにするため、国が制度を整備した証拠です。
ファクタリングは、法律上の根拠に加えて政策的にも推進されており、中小企業経営にとって安全で有効な資金調達手段であることがわかります。
「違法」イメージの正体:ファクタリングを装うヤミ金融の手口
ファクタリングは法的に認められた取引ですが、「違法」「危険」というネガティブな印象が広く浸透しています。
その原因は、ファクタリングの名を悪用して違法な貸付を行う、貸金業登録のない金融業者(ヤミ金)の存在にあります。
本当の敵は「偽装ファクタリング」
悪徳業者は資金繰りに困った事業者を狙い、「ファクタリング」と称して実際には法外な高金利でお金を貸し付けます。
彼らの目的は、債権を買い取ることではなく、貸金業法や出資法といった法律を回避して暴利を得ることです。
こうした業者が横行しているため、「ファクタリング=怪しい」という誤解が広まってしまいました。
金融庁が発する警告と公式見解
日本の金融システムを監督する金融庁は、公式ウェブサイトで「ファクタリングの利用に関する注意喚起」を発表しています。
ここで特に重要なのは、「契約書に『債権譲渡契約』と記載されていても、実質が貸付と同じであれば貸金業に該当する」という指摘です。
たとえば、売掛金の回収リスクがファクタリング会社に移らず、最終的に利用者が負担する場合(償還請求権あり契約)は、形式上はファクタリングでも、実態は「売掛債権を担保とした貸付」と見なされます。
金融庁はこうした取引を違法と判断し、事業者に注意を呼びかけています。
本記事でも金融庁サイトへのリンクを紹介するのは、公的機関の情報を直接確認し、安全な取引をサポートするためです。
【参考リンク】
金融庁:ファクタリングの利用に関する注意喚起
貸金業法違反という重大犯罪
日本では、繰り返し継続的に金銭を貸し付ける事業を行う場合、国または都道府県への「貸金業」登録が法律で義務付けられています。
無登録で貸金業を営むことは、それだけで刑事罰の対象となる重大な犯罪です。
また、登録済みの業者であっても、利息制限法や出資法で定められた上限金利(元本額により年15~20%)を超える金利を取ることは禁じられています。
ヤミ金業者はこれらすべてを無視し、極めて高い利息を違法に徴収します。
政府は経済産業省が正規ファクタリングを推進する一方で、金融庁がこうした違法行為を取り締まり、市場の健全化を図っているのです。
この背景を理解することが、事業者自身を守る第一歩となります。
【事業者向け自己防衛マニュアル】悪徳業者(ヤミ金)を見分ける8つの危険なサイン
ここからは、事業者が安全なファクタリング会社と違法なヤミ金を見分けるための具体的な方法を紹介します。
以下の「8つの危険なサイン」は、貴社を違法業者から守るための実践的なチェックリストです。
まずは、両者の違いを一目で理解できる比較表をご覧ください。
表1:合法なファクタリングと違法なヤミ金の見分け方
| 特徴・サイン | 合法なファクタリング | 違法なヤミ金(偽装ファクタリング) |
|---|---|---|
| 1. 手数料 | 相場内(2社間: 8~18%、3社間: 2~9%)で透明性が高い | 相場を大幅に超える法外な率、または不透明 |
| 2. 契約書の種類 | 「債権譲渡契約書」 | 「金銭消費貸借契約書」または契約書自体を渡さない |
| 3. 償還請求権 | 「なし」(ノンリコース)が原則 | 「あり」(リコース)を要求 |
| 4. 回収金の支払い | 売掛先から回収後、一括で送金 | 「分割払い」を提案 |
| 5. 対象債権 | 事業者の売掛債権 | 個人の給与を扱う(給与ファクタリング) |
| 6. 審査 | 売掛先の信用力を重視し厳正な審査あり | 「審査なし」「誰でもOK」を謳う |
| 7. 会社情報 | 住所・固定電話番号を明記し実在する | 住所不明、携帯番号のみ、サイトがない |
| 8. 契約書の控え | 必ず控えを交付する | 控えを渡さない、撮影も拒否 |
それでは、各項目を詳しく解説します。
危険なサイン①:法外な手数料
正規の手数料相場は以下が目安です。
- 2社間ファクタリング:8~18%
- 3社間ファクタリング:2~9%
これを大きく超える30~40%の手数料を提示された場合は、ほぼ間違いなくヤミ金です。
たとえば「手数料10%」で30日後に回収される債権を買い取る場合、年率換算すると約121.7%という驚異的な利率となります。
手数料が相場から逸脱していれば、それは最もわかりやすい危険信号です。
危険なサイン②:契約書が「金銭消費貸借契約書」
契約書の名称は、その取引の性質を決定づけます。
正規のファクタリングでは、必ず「債権譲渡契約書」を交わします。
一方、「金銭消費貸借契約書」は法律上「お金の貸し借り」を意味します。
契約書がこの形式であれば、実質はファクタリングではなく融資です。
契約書が交付されない、または内容が不明確な場合も同様に危険です。
危険なサイン③:「償還請求権あり」を要求
償還請求権(しょうかんせいきゅうけん)とは、売掛先が倒産して代金が回収できない場合に、ファクタリング会社が利用者に代金返還を請求できる権利です。
- 償還請求権なし(ノンリコース)
売掛金の回収リスクはファクタリング会社が負います。これが正規のファクタリングです。 - 償還請求権あり(リコース)
回収リスクを利用者が負います。これは実質的に売掛債権を担保とした融資と同じです。
貸金業登録をしていない業者が「償還請求権あり」の契約を行うことは、明確な法律違反です。
契約前には必ず「ノンリコース」の記載を確認してください。
危険なサイン④:回収金の「分割払い」
2社間ファクタリングでは、売掛先から入金があった時点で全額を一括送金するのが原則です。
業者が「分割で支払ってよい」と持ちかけてきたら注意が必要です。
これは実質的に融資の返済であり、ヤミ金が利用者を借金漬けにする典型的な手口です。
危険なサイン⑤:「給与ファクタリング」を扱っている
給与ファクタリングは、個人の給与を対象とするサービスです。
金融庁や最高裁判所の判断により、これは「貸金業」に該当します。
貸金業登録をしていない業者が給与ファクタリングを行うのは、100%違法です。
もし検討している会社が給与ファクタリングも取り扱っている場合は、即座に関わるのをやめましょう。
危険なサイン⑥:審査が甘すぎる
「審査なし」「誰でもOK」などと宣伝する業者は、ほぼ確実に悪徳業者です。
正規の会社は、利用者ではなく売掛先の信用力を厳しく審査します。
なぜなら、売掛先が倒産すればリスクを負うのはファクタリング会社だからです。
甘い審査は、回収を利用者から強引に行うつもりである証拠です。
危険なサイン⑦:会社情報が不透明
信頼できる会社は、自社情報を隠しません。以下の場合は注意が必要です。
- 連絡先が携帯電話番号しかない
- 記載されている住所がレンタルオフィスや実在しない場所
- 公式サイトがなく、SNSや掲示板だけで勧誘している
これらは摘発を逃れるために身元を隠している可能性があります。
危険なサイン⑧:契約書の控えを渡さない
契約書の控えを交付しない業者は非常に危険です。
「社内規定で持ち出し禁止」などの理由で控えを拒否されたら、即座に取引を中止しましょう。
これは違法契約の証拠を残さないための典型的な手口です。
もし危険な業者に遭遇してしまったら:相談窓口と対処法
万が一、悪徳業者と関わってしまったり、契約内容に不安を感じたりした場合は、一人で悩まずに専門機関へ相談しましょう。
違法な業者に対しては、迅速かつ毅然とした対応が必要です。
公的な相談窓口
以下は、国や地方自治体が設置している公式相談窓口です。
悪質な取り立てや法外な手数料請求に悩んでいる場合は、すぐに連絡してください。
- 金融庁 金融サービス利用者相談室
ファクタリングを装ったヤミ金融に関する相談を受け付けています。専門の相談員が対応します。 - 警察相談専用電話「#9110」
脅迫的な取り立てや身の危険を感じる場合は、ためらわずに警察に相談しましょう。 - 日本司法支援センター(法テラス)
経済的な理由で弁護士相談が難しい場合でも、無料で法律相談が受けられます。
契約解除や過払い金請求など、法的な解決策についてアドバイスを受けられます。 - 各都道府県の貸金業担当課・消費生活センター
地方自治体にも、悪質金融業者に関する相談窓口が設けられています。
最善策は「関わらないこと」
最も重要なのは、少しでも怪しいと感じたら契約しないことです。
前章で紹介した「8つの危険なサイン」のうち一つでも当てはまれば、どれほど魅力的な条件を提示されても即座に断るべきです。
資金繰りが厳しいときは冷静な判断が難しくなりがちです。
しかし、ヤミ金と関われば一時的に現金が手に入っても、違法な取り立てや法外な利息によって、事業そのものが破綻するリスクが高まります。
結論:正しい知識で、ファクタリングを安全・有効な経営戦略に
ここまでで、ファクタリングに関する漠然とした不安は、明確な知識へと変わったはずです。
最後に重要ポイントを整理します。
- ファクタリングは合法
民法第466条で定められた「債権譲渡」という正当な権利に基づき、経済産業省も推奨する中小企業向け資金調達手段です。 - 危険なのはヤミ金
問題の根源は、ファクタリングを装って高金利貸付を行う違法業者にあります。 - 判断基準は「売買」か「貸付」か
「償還請求権の有無」が、合法か違法かを見分ける最重要ポイントです。
今回紹介した「8つの危険なサイン」を活用すれば、安全な業者を選び抜き、事業を守ることができます。
ファクタリングを正しく理解すれば、怪しい金融サービスではなく、キャッシュフローを改善し事業成長を支える有効な経営戦略ツールとなるでしょう。
次のステップ
危険を回避する知識を得たら、次は「数ある優良企業から、自社に最適な一社を選ぶ」段階です。
以下の記事では、手数料、スピード、専門性などの観点から、優良なファクタリング会社を見極めるための10項目チェックリストを紹介しています。